わたしの一冊 ~理学部教員の本棚より~
皆さんは、心に響く一冊や、新たな発見をもたらしてくれる本との出会いがありますか?
今回は、理学部の教員たちが自らの人生や研究に深く影響を与えた本を語る特集記事をお届けします。どの本も、単に知識を得るだけでなく、思考を深め、視野を広げ、時には人生の指針となるような力を持っています。理学部の多様な学科で活躍する教員たちの「本棚」から、彼らがどのように本と向き合い、どのような影響を受けてきたのかをぜひご覧下さい。
板谷 昌輝 助教(化学科)
1994年石川県出身。ブダペスト工科経済大学でポスドクを経て、2024年1月に北大着任。美しいキャンパスと研究環境が気に入っている。小中高時代は野球三昧で、ポジションはキャッチャー。今年度の化学科野球大会では研究室を4位に導いた(例年と比べて大躍進)。
自己組織化への興味
モノが勝手に構造や組織、秩序を作り上げる現象を「自己組織化」と言います。例えば、一つの受精卵が細胞分裂を繰り返して組織を作り、体ができ上がる過程や、雪の結晶が規則正しい形に成長する仕組み、魚や鳥が集団で動く様子も自己組織化の具体的な例です。生命の起源も同じです。バラバラに存在していた原子や分子が、特定の条件下で秩序を持った構造を形成し、やがて生命としての特徴を持つようになりました。とても興味深いと思いませんか?今回紹介する「自己組織化とは何か第2版」との出会いがきっかけで、僕は自己組織化にすっかり魅了されました。一般的な条件下での化学反応はエントロピーの増大、つまり無秩序な状態へ向かうのが基本原則です。しかし特定の条件下では、無秩序な状態から秩序が生まれることもあります。冒頭で例を挙げたように「自己組織化」とは非常に多岐に渡る言葉です。この本は現象を分かりやすく解説しており、高校生や大学生にお勧めします。
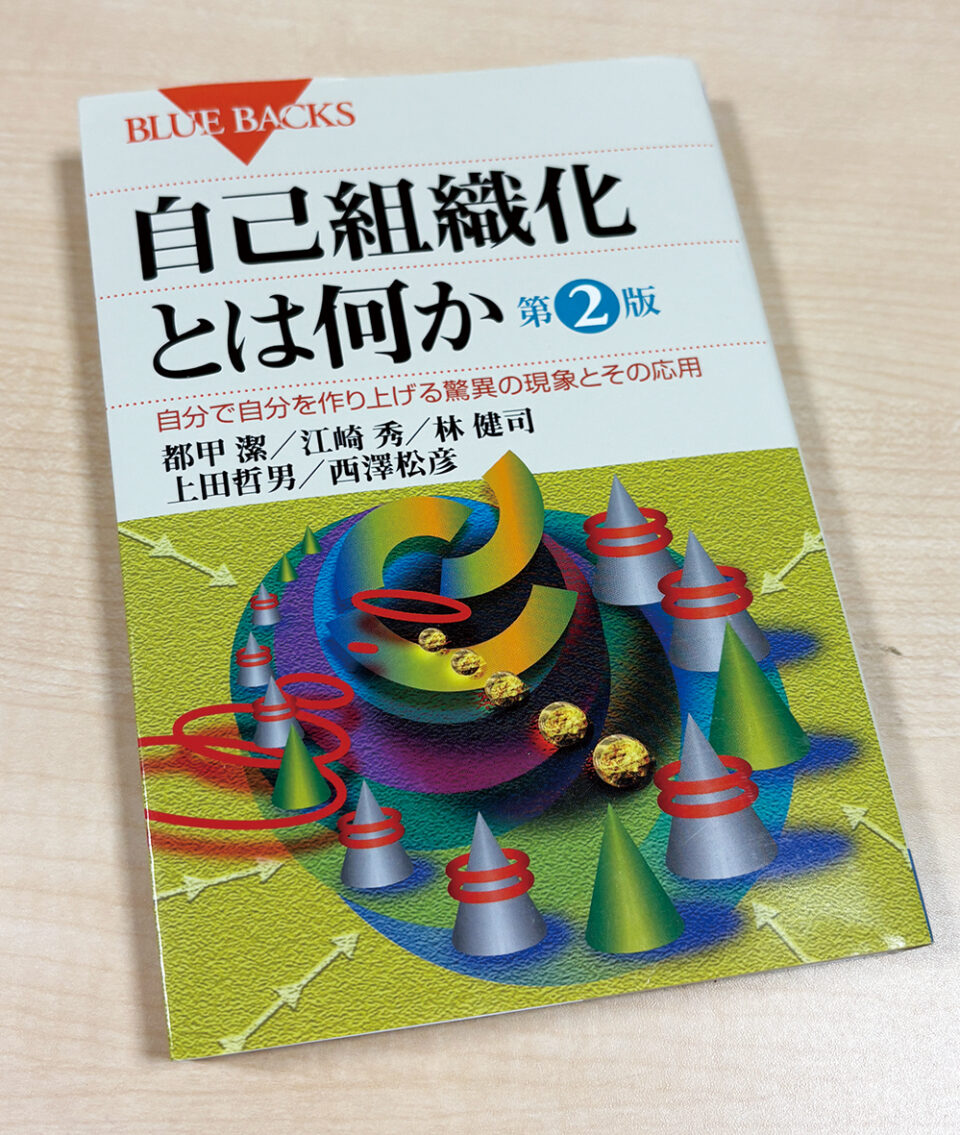
非平衡状態と自己組織化
もう一つ重要な概念として、この本では「熱力学的平衡」と「熱力学的非平衡」を紹介しています。平衡状態とは、例えばA + B ⇄ Cのような可逆反応において、正反応と逆反応の速度が等しくなり、全体として見かけ上の変化がない状態のことを指します。溶液や物質を混ぜて放置しただけのビーカー内(物質やエネルギーの恒常的な流れがない条件下)では平衡状態が成立しますが、自然界のほとんどの現象は、エネルギーの流入や流出がある非平衡状態です。人間も食事や呼吸をして、外部とエネルギーのやり取りをして生きています。エネルギーや物質の流入出がある非平衡状態だからこそ、自ら秩序を作る自己組織化が起こるのです。
界面の化学現象を研究
現在、僕はある物質の2つの熱力学的な層の間(界面)に生まれる化学現象を研究しています。特に物質を電気化学的に反応させる際に、電極と溶液の間の界面で起こる化学現象に注目しています。電極反応は、溶液からの物質や電極界面での電子を介して常に物質・エネルギーのやり取りが行われる中で化学反応が進行するため、非平衡現象として捉えることができます。僕の研究の目的は、これら電気化学反応の複雑なメカニズムを解明し、より精密に制御することです。自然界の様々な秩序は、いずれも物理的な原理に基づいているはずです。現象の背景にある原理原則を探ることで、新たな自己組織化現象を生み出す手がかりを得たいと考えています。最終的には、より少ないエネルギーで効率的に様々なモノを作る人工システムの開発を目指しています。

人も経験から自己が組織化されるはず
人はそれぞれ得意なことやできることが異なります。お互いに尊重し合うためにも、自分がどのような人間なのかをよく知ることが大切です。情報にあふれている現代だからこそ、自分の定規(価値観)をしっかりと持ち、自分に合った道を見極めてほしいです。そうすれば自ずと成長していけると思います。僕も大学生の頃、友人と遊んだり、本を読んだり、アルバイトをしたり、さまざまな経験を通して考えを巡らす中で、段々と自己組織化してきたと感じています。
紹介した本
『自己組織化とは何か 第2版‒自分で自分を作り上げる驚異の現象とその応用』都甲潔/江崎秀/林健司/上田哲男/西澤松彦(著)、講談社ブルーバックス
理学部広報誌「彩」第12号(2025年2月発行)掲載。>理学部 広報・刊行物
※肩書、所属は、広報誌発行当時のものです。



