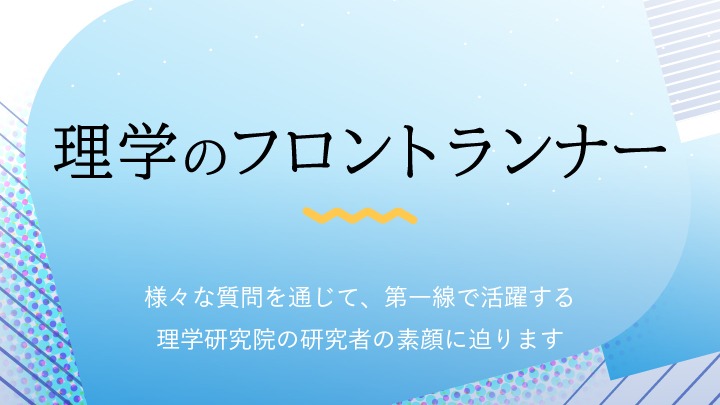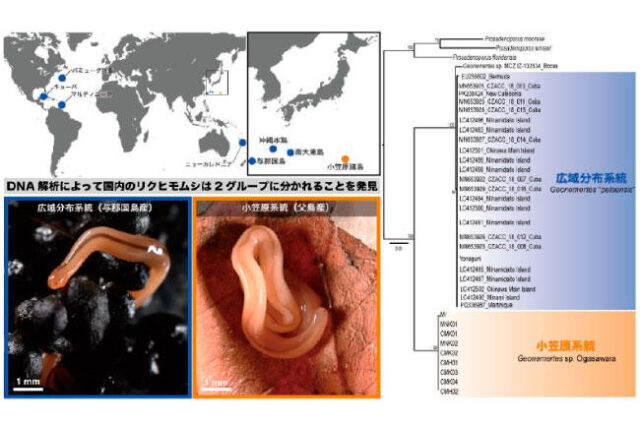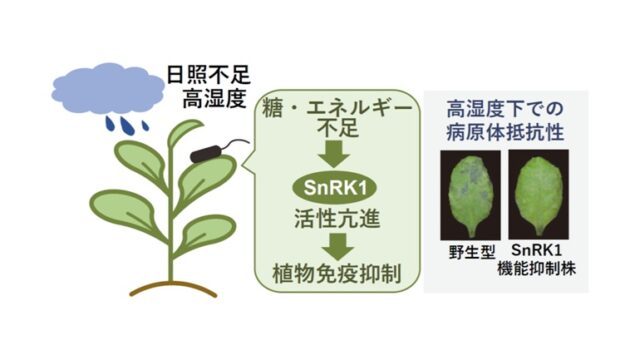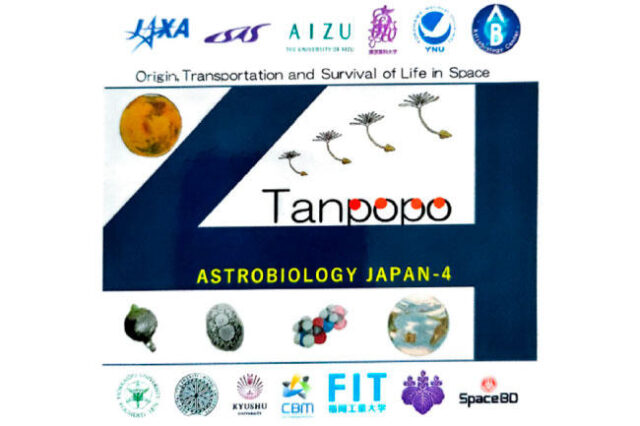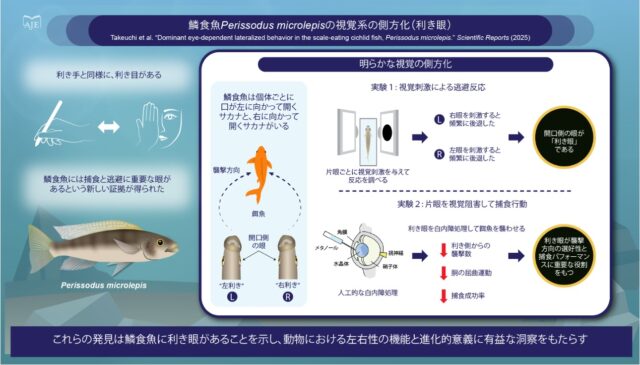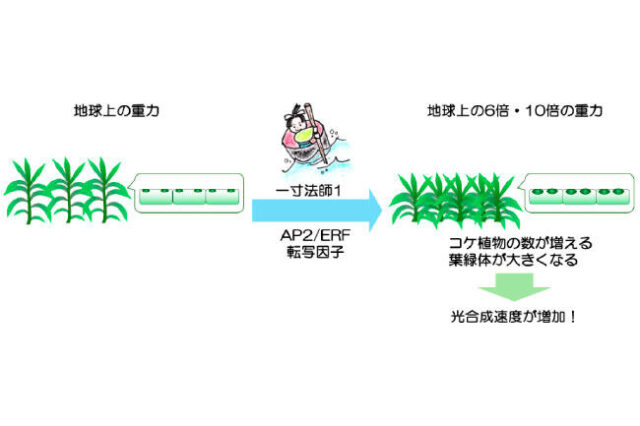西日本にて海産等脚目甲殻類「ウミクワガタ」の 5新種と1日本初記録種、1再発見種を発見

鳥取県立山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館、北海道大学、京都大学との共同研究により、沖縄県から鳥取県にかけて、新種の甲殻類が多数見つかり、その研究成果が論文で発表されました。
<ウミクワガタについて>
- 等脚目(ワラジムシ目)ウミクワガタ科に属する甲殻類の仲間。
- 世界から12属約240種、日本近海からは6属37種が知られていた。
<研究の概要>
- 1995〜2023年にかけて、複数の研究機関の練習船や調査船による調査航海で得られた標本を精査したほか、スキューバダイビングによって成体や幼生を採集、地元漁師の方々から展示用に提供いただいた魚から幼生を採集した。一部幼生については研究室で飼育を行い、脱皮させることで成体を得た。
- 得られた標本を各種顕微鏡で観察し、国内外で知られる種と、頭部や腹尾節(「しっぽ」のように見える部位の後端の三角形の部位)などの形態を比較することで、5種が名前のついていない未記載種(つまり新種)、1種が日本初記録、1種が1926年に長崎県で見つかって以来、99年ぶりの再発見となる種であることを明らかにした(以下参照)。そのほか3種の既知種を追加報告した。
【新種】ティダウミクワガタCaecognathia tida・・・奄美大島沖の水深290mから見つかった。全体的に丸みを帯びた形態が特徴で、和名・学名ともに沖縄地方の太陽を意味する言葉である「ティダ」に由来する。
【新種】フシメウミクワガタCaecognathia inferoculus・・・熊本県天草市沖の水深193~213m から見つかった。ウミクワガタ類ではほとんどの種が複眼は頭部の横にあり背面から見えるが、本種では下に向いており背面からは見えないことが特徴で、和名・学名もその特徴に由来する。
【新種】リュウキュウイソウミクワガタGnathia hayashiae・・・宮古島と沖縄島の潮間帯から見つかり、個体数も多い普通種。和名は沖縄地方(琉球列島)の浅い環境(磯)に由来し、学名は琉球大学で本種の生態学的調査を行ってきた大学院生に献名した。メス成体や幼生の形態も併せて記載した。
【新種】トヨシオウミクワガタGnathia toyoshiomaruae・・・奄美大島沖の水深 302mから1個体のみ見つかっている。広島大学の練習船豊潮丸に献名した。
【新種】タジリウミクワガタGnathia tajirana・・・沖縄近海から鳥取県沖の30〜202mから見つかった。和名・学名ともに、採集地の1つである田後の名前に因む。
【日本初記録種】マエカドウミクワガタGnathia koreana・・・韓国南部から見つかり、国内では九州の宮崎県沖から鳥取県沖の水深20〜484mから見つかっている。和名の「マエカド」は頭部前方に張り出した突起があることから新たに提唱した。
【99年ぶりの再発見】ヨコナガウミクワガタGnathia consobrina・・・フランスの研究者が 1926年に報告して以来、長崎県から見つかっていること以外に詳細が分かっていなかった。九州の離島の馬毛島沖から鳥取県沖の水深20〜119mで見つかった。成体は海底の付着生物の中から見つかった。和名は頭部の幅が広いことに因む。
<論文を発表した学術雑誌>
雑誌名:Bulletin of Marine Science(マイアミ大学から出版されている海洋科学紀要)
論文名:Review of the Gnathiidae (Crustacea: Isopoda) of western Japan with a description of five new species, one redescription, and one new Japanese record.
(西日本におけるウミクワガタ科甲殻類のレビュー:5新種、1種の日本初記録、1種の国内記録)
著者名:太田悠造(鳥取県立山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館)・角井敬知(北海道大学)・下村
通誉(京都大学)
掲載日:2025年3月31日(オンライン公表)
DOI:10.5343/bms.2024.0086
プレスリリースはこちら