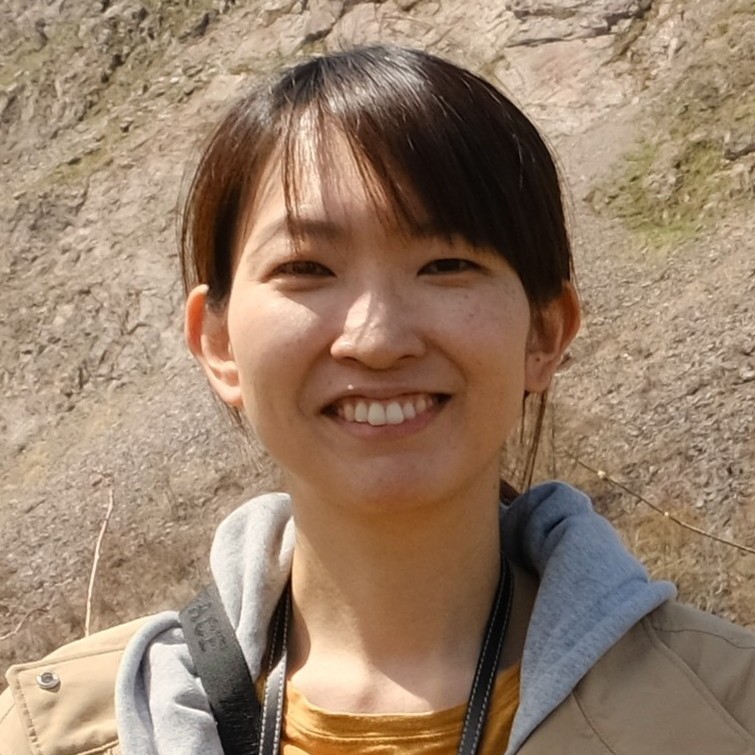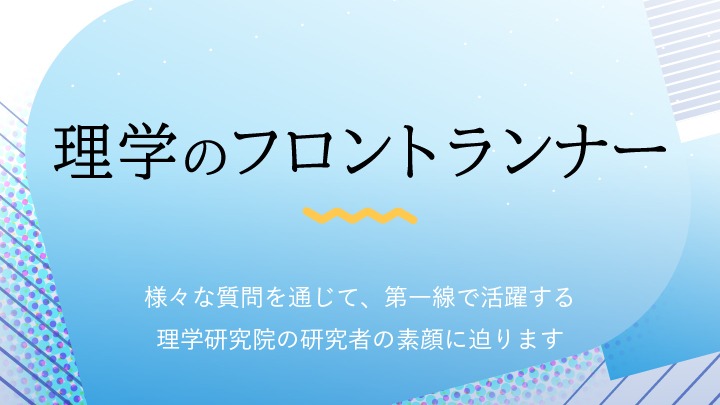| 研究テーマ | 火山の噴出物を構成する結晶・ガラスといった物質をナノスケールから調べることで噴火のメカニズムの解明を目指します |
| 研究分野 | 火山学, 火山岩岩石学, 結晶成長学 |
| キーワード | マグマ, ガラス, 結晶, 核形成, 結晶成長, 火山 |
研究紹介
「火山の噴火様式は何によって決定されるのか?」は、火山学における最大の未解決問題の一つです。一般に噴火様式は、マグマの粘性によって非常に異なると言われています。低粘性の玄武岩マグマはハワイの火山のように噴き出して流れる溶岩流噴火になるなど比較的穏やかである一方、高粘性のマグマは、1991年のフィリピンのピナツボ火山のように噴煙柱があがるプリニー式噴火という大噴火や、雲仙普賢岳のように溶岩ドームを形成し、これが崩壊して火砕流になるなど、マグマの破砕(微細化)がおこりやすく、爆発的となりやすいと言われています。しかし低粘性の玄武岩マグマであっても、富士山(Fig.1)の1707年の宝永噴火で、江戸(東京)にまで火山灰(マグマが破砕し、粉々になったもの)を降らせたように、プリニー式の大噴火が起こることが世界の火山でも確認されています(タラウェラ火山やエトナ火山など)。低粘性の玄武岩マグマにも関わらず、なぜマグマの破砕が起こり大噴火となるのかは現在でも論争中です。また、一つの火山、同じマグマでも噴火様式が遷移することは珍しくなく(新燃岳2011年噴火ではサブプリニー式噴火から火口に溶岩をためる噴火、ブルカノ式噴火と移行しましたがマグマの組成は同じでした)、何がそれを支配しているのかは未だによくわかっていません。
このような火山噴火のメカニズムを解明するために、物質科学の視点から研究を行っています。特に、ナノ結晶という新しい観点から火山の噴火過程を理解する研究を進めてきました。また,マグマ中での結晶化メカニズムに関して,近年,水溶液系で発見された非古典的な核形成経路にも着眼して研究を進めています。
代表的な研究業績
| 学位 | 博士(理学) |
| 自己紹介 | 都立高校出身です。小中高とバスケットボールをしていましたが、ドクターストップで高校の途中からオーケストラでホルンを吹き始めました。大学3年生のときに樽前山の溶岩ドームをみて感動し、火山研究の道に進みました。 |
| 学歴・職歴 | 2012年:東北大学理学部地球惑星物質科学科 卒業 2014年:東北大学大学院理学研究科地学専攻修士課程 修了 2017年:東北大学大学院理学研究科地学専攻博士課程 修了 2017年:東北大学理学部・理学研究科 研究支援者 2018-2023年:東北大学大学院理学研究科 地学専攻 助教 2023-2024年:東北大学 高度教養教育・学生支援機構 教育内容開発部門 自然科学教育開発室 助教 (兼)理学研究科 地学専攻 助教 2024-2025年:東北大学大学院理学研究科 地学専攻 助教 2025年-:現職 |
| 所属学会 | 日本地球惑星科学連合(JpGU), 日本鉱物科学会, 日本火山学会, 日本顕微鏡学会 |
| 居室 | 理学部6号館 |