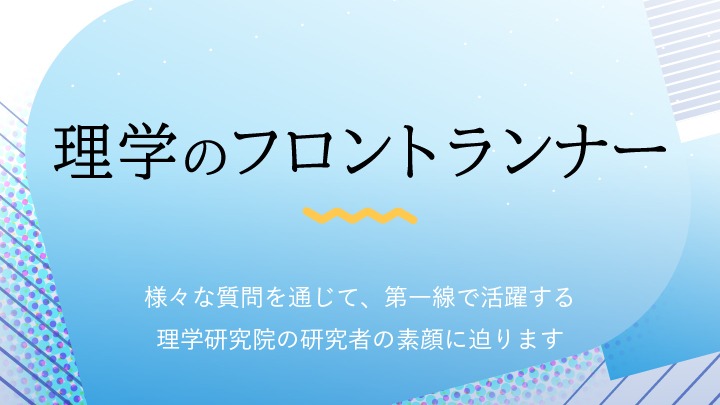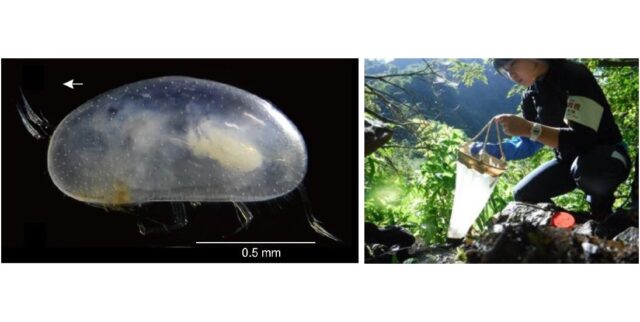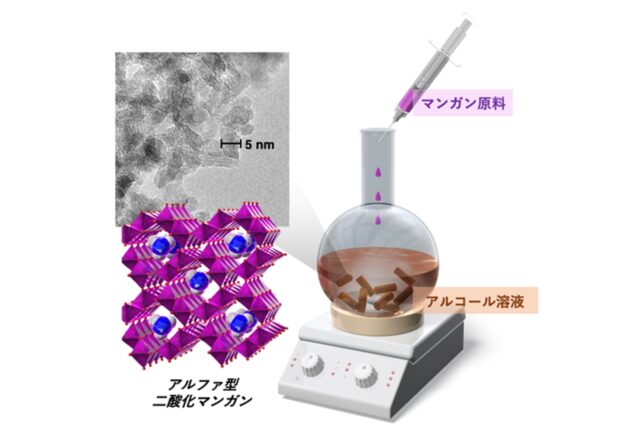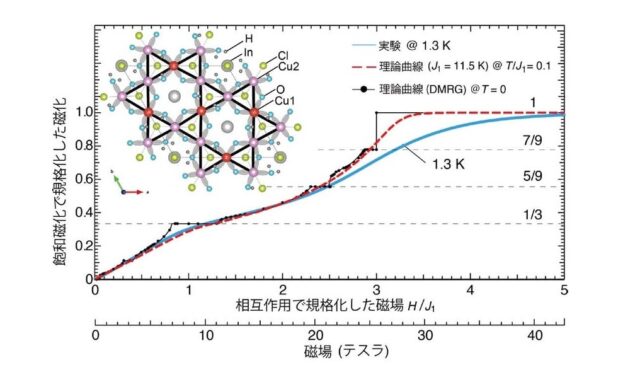永井 隆哉 教授
北海道大学大学院理学研究院は、1930年に北海道帝国大学理学部として、農学部、医学部、工学部に次いで学内4番目に創設され、当初は、数学、物理学、化学、地質学・鉱物学、植物学、動物学の6学科体制でスタートしました。創設当初に建設された理学部の建物は、札幌初の本格的なコンクリート造建築であり、現在も理学部本館としてその姿を残し、北海道大学総合博物館としても広く世界からの訪問者を受け入れています。建物中央にある「アインシュタインドーム」と呼ばれる吹き抜けには「果物」「ヒマワリ」「こうもり」「ふくろう」のレリーフが飾られており、それぞれ朝・昼・夕・夜を象徴しています。これらは、研究・教育に昼夜を問わず取り組む決意を表して、創立当時の「理学部を理学研究のメッカにしたい」という熱い志を今に伝えています。
このような先人の思いとともに歩んできた理学部は、2030年に創立100周年を迎えます。その間、1947年に北海道大学理学部と改称、1953年に大学院理学研究科を設置。その後、1990年代以降の大学院重点化・国立大学法人化を経て、2006年には研究組織(大学院理学研究院)と教育組織(大学院理学院)に分割・再編されました。現在、理学研究院は数学・物理学・化学・生物科学・地球惑星科学の5部門から構成され、さらに附属センターとして地震火山研究観測センター・ゲノムダイナミクス研究センター・原子核反応データベース研究開発センターを擁する総勢300名以上のスタッフが所属する北海道大学内でも有数の規模を誇る研究組織となっています。
理学研究院は、長い歴史の中で常に最先端の理学研究を推進してきました。例えば、中谷宇吉郎博士による世界初の人工雪の作製、鈴木章博士(2010年ノーベル化学賞受賞)によるカップリング反応の開発などは、その代表例です。近年では、北海道大学発の研究成果プレスリリースの約20%が理学研究院の研究成果であり、その研究力の高さを示しています。さらに、2018年には世界トップレベル研究拠点(WPI)として「化学反応創成研究拠点(ICReDD)」が発足、化学反応が関わる将来の世界を一変させる今後の成果をぜひご期待ください。
理学研究院は研究組織であると同時に、次世代の人材を育成するという重要な役割も担っています。本研究院に所属する教員は、現在、理学部の数学科・物理学科・化学科・生物科学科(生物学専修)・地球惑星科学科の5学科の学部教育を担当し、大学院教育では理学院・生命科学院・総合化学院の3つの学院(教育組織)において大学院生を指導しています。また、日本人学生と留学生が共に学び、グローバルな視野を持ったリーダーの育成を目指した特色ある教育プログラムとして、以下の5つを展開しています。
・「物質科学フロンティアを開拓するAmbitiousリーダー育成プログラム」(2013年~)
・「Integrated Science Program(ISP)」(2017年~)
・「スマート物質科学を拓くアンビシャスプログラム」(2021年~)
・「複眼的高度DX人材育成プログラム」(2023年~)
・「地球規模の課題解決に資する生命科学研究者育成プログラム」(2024年~)
加えて、これらの研究・教育体制を支援するために、教育研究戦略室(研究・教育の将来戦略支援)、国際化支援室(海外大学との連携支援、留学生・教職員・海外からの訪問者支援)、広報企画推進室(広報誌「彩」やWEB・SNSによる情報発信)など、独自の強力なサポート体制を整備しています。
創設時から脈々と受け継がれてきた先人たちの志を胸に、理学研究院は「北の大地の理学のトップランナー」として、世界へ最先端の研究成果を発信し続け、魅力的な教育プログラムを展開してきました。理学の研究は、必ずしもすぐに社会に応用されるわけではありません。しかし、アインシュタインの相対性理論が後に現代物理学の礎となったように、今ここで生まれている研究が、数年後、あるいは100年後に世界を変える可能性を秘めています。それこそが理学研究の醍醐味です。一方で、現代社会においては、気候変動・エネルギー問題・医療・AI・情報技術・材料科学・ナノテクノロジーなどに関する喫緊の課題の解決にも、理学の知見が求められています。私たちは、今後も研究を通じて多様な要請に応えるとともに、幅広い分野で活躍できる人材の育成に注力することで、未来の科学の発展と社会への貢献を目指して邁進してまいります。
皆さまの変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。